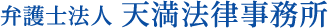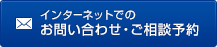職務著作
2008年2月25日 知的財産権:特許・実用新案・意匠・商標・著作権・不正競争防止法
職務著作とは、著作権法第15条の要件を満たせば、実際に著作物を作成していなくても、法人その他の使用者(これらを「法人等」といいます。)が著作者となり、著作権のみならず著作者人格権を取得することをいいます(例えば、従業員等が描いた絵画などつき、法人等がその絵画などの著作権等を原始的に取得することなどです。この点は、特許における職務発明とは異なります)。
その要件は、①法人その他使用者の発意に基づくこと、②法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物であること、③法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること、④作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないことです(ただし、プログラムの著作物であれば、③は不要です)。
そして、実務上、問題になることが多いのは②の要件についてです。とりわけ「法人等の業務に従事する者」にはどういう者があたるか問題となります。
最高裁は、法人等と雇用関係にある者が「法人等の業務に従事する者」に当たることは明らかであるとしつつ、雇用関係の存否が争われた場合には、法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに、法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり、法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを、業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して判断すべきであるとしました(最判平成15年4月11日最高裁HP(アール・ビー・ジー事件))。
この最高裁判決を読む限りでは、雇用関係にない者、例えば業務受託者や請負人は射程の範囲外であると考え、これらの者に業務従事性が認められる余地があり得るともいえます。もっとも、最高裁判決の主眼は、業務従事性を実質的に判断するという立場であり、契約の名称が業務委託契約や請負契約となっていても、業務態様や指揮監督の有無、対価の額、支払方法などの具体的事情によっては、実質的に雇用関係であるとして、業務従事性が認められることになると考えられます。
従って、法人等とその業務に従事する者との具体的実質的関係がポイントであり、具体事案の集積が待たれます。