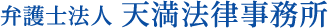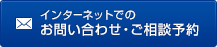事業承継(事前対策)その2
2013年7月29日 事業承継、M&A
1 はじめに 事業承継(事前対策)その1 において説明したとおり、 最もとりやすい対策としては、ずばり「遺言書を作成する」ことが考えられます。 2 遺言書を作成する場合の注意点 (1)公正証書遺言を利用する ア 自筆証書遺言の問題点 ①民法上形式が厳格に定められており、この形式を満たしていないと無効と などの問題があります。 イ 公正証書遺言の場合 また、 ❷自筆証書遺言のように検認の手続きを経る必要はなく、 このように、後に遺言が無効とされるリスクを減らすという点では、公正証書 (2)遺言書の中で全ての遺産の帰属を決めておく 遺言書で帰属の決められていない遺産があると、当該財産についての遺産分割 (3)遺言書の中で遺言執行者を指定しておく ⅰ相続人が勝手に相続財産を処分することなどを防止する(勝手に処分した などのメリットがあります。 3 遺言による対策の限界 (1)撤回の可能性 (2)遺留分減殺請求の可能性 ⅰ被相続人から(とりわけ後継者以外の)相続人に対して、そのような あるいは ⅱ被相続から推定相続人に対して、自分の考えを直接話してもらう、 ⅲ遺言の中に同様の内容を付加的に入れておく、 いずれの方法が適切かは、事案により異なりますので、その事案に適した方法
遺言書が作成されていない場合には、遺産のうちどれを誰に帰属させるかは
遺産分割手続により決めることになります。
しかし、残念ながら、往々にして相続人間に意見の対立があり、協議がまとまらず、
遺産の帰属が決まるまでに数年かかることもよくあるところです。
このような事態を避け、円滑・迅速に事業承継を行うためには、どのようにすれば
よいのでしょうか。
遺言にも、後述のとおり一定の限界はありますが、有効かつ適切な遺言書を作成
することにより、遺産分割手続を避けることのできるケースも多いです。
遺言書は、自分で作成することもできます(自筆証書遺言)が、「本人の
筆跡でない」などと主張されることも多く、トラブルになりやすいといえます。
また、自筆証書遺言の場合、
されるおそれがある、
②必ず家庭裁判所において検認の手続を経なければならず、検認前に勝手に
開封したことにより効力が否定されるおそれがある、
③保管の仕方によっては紛失のおそれがある、
これに対し、公正証書遺言の場合には、遺言の内容を筆記するのは公証人
ですので、
❶形式を満たしていないが故に無効とされることがない分、自筆証書遺言の
場合と比べ、後に遺言が無効とされる可能性が低いといえます(無効とされる
のは、認知症等により、ご本人の判断能力が低下しており、遺言の内容を理解
できる状態ではなかったような場合に限られます)。
❸原本が公証役場に保管されるため、紛失のおそれもありません。
遺言の方が優れていますので、遺言を行う場合には、可能な限り公正証書による
べきです。
手続が必要となります。これでは、遺言書を作成した意義が薄れてしまいます。
また遺産分割手続における意見の対立を契機として、遺言書の効力をめぐる
トラブルが生じるおそれも否定できません。
さらに、遺言書と遺産分割手続が併存する結果、とりわけ遺留分の問題が
生じる場合には、かえって相続人間の利益調整方法等が複雑になるという弊害も
生じます。
そのため、遺言書を作成するのであれば、遺言書の中で全ての遺産の帰属を
決めておくべきです。また、万が一記載漏れや知られていない遺産があった場合
に備え、例えば、最後に「上記以外の財産は、●●に相続させる。」といった条項
を入れておくことが考えられます。
遺言の内容によっては、遺言執行者でなければ執行できない事項(認知、推定
相続人の廃除等)があります。このような事項が含まれているにもかかわらず、
遺言で遺言執行者が指定されていない場合には、家庭裁判所に対し遺言執行者の
選任の申立てをしなければならないなど、手間と時間がかかります。
また、そうでなくとも、遺言執行者を指定することにより、
場合には無効となります)、
ⅱ本来相続人全員で協力しなければできない手続(の一部)が遺言執行者限り
で行えるようになり、相続人の負担が軽減される
そのため、遺言書の中で遺言執行者を指定しておく方がよいでしょう。
もっとも、遺言による対策には主として以下のような限界があります。
遺言の内容は、新しい遺言によりいつでも撤回・変更することができます。
そのため、とりわけ生前から被相続人の財産をめぐる争いが顕在化している
ような場合には、一部の推定相続人が被相続人の判断能力の低下につけこんで、
自己に有利な公正証書遺言を新たに行わせるというようなケースも珍しく
ありません。
このような場合には、原則として、後の公正証書遺言により、先の(公正証書)
遺言が撤回・変更されたということになってしまいます。これを覆すためには、
例えば、後の公正証書遺言を行った当時、被相続人の判断能力が低下しており、
遺言の内容を理解できるような状態ではなかったということを立証する必要が
ありますが、この立証は容易ではありません。
遺産の処分は原則として所有者であるご本人(被相続人)の自由に委ねられて
いますが、民法は共同相続人間の公平な財産相続等を図る観点から、遺留分と
いうものを定めています。遺言により自己の遺留分を侵害された相続人は、
遺留分減殺請求権を行使することにより、その遺留分の限度で、遺言の効力を
否定することができます。
そのため、遺言書を作成する場合には、例えば、事業と関係のない財産のうち、
各自の遺留分に相当する部分を後継者以外の相続人に帰属させるなど、できる
限り後継者以外の相続人の遺留分を侵害しないような内容とする方が安全です。
それが難しい場合には、後継者以外の推定相続人に、遺留分の放棄手続
(家庭裁判所の許可が必要)をとってもらうことも考えられます。
(もっとも、家庭裁判所は、
ⅰ申立てが遺留分権者の自由意思に基づくものであるか、
ⅱ放棄理由に合理性・必要性があるか、
ⅲ放棄に代償性があるか(放棄に見合った対価を得ているか)
を考慮して、許可するか否かを判断するため、必ず許可されるとは限りません。)
また、被相続人の意思をはっきりと示されると、なかなか反対しづらいと
いう事実上の効果を期待して、例えば、
遺言にした理由、被相続人の思いを説明する手紙を書いてもらったり、
といった方法も考えられます。
を慎重に検討する必要があります。